日本科学振興協会シンポジウム「研究公正に必要な取り組みとは?」(詳細記録あり)
2022年6月23日 15:00-16:30 (Zoom webinar) 田中智之(京都薬科大学)、中村征樹(大阪大学) 共催:科学技術振興機構・社会技術研究開発センター(JST-RISTEX)「科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム」
シンポジウムの狙い
質の高い研究を実施するためには、研究公正が積極的に推進される環境が必要であるが、当事者である研究者を含め、このことは十分に認識されているとは言い難い。そこで、研究者、行政、そして最終的には社会が、どのようにこの問題に取り組めば良いのかについて議論する。具体的なテーマとしては、1)倫理教育やルールの効果と限界、2)誰が研究公正を進めるか、3)日本版ORIの可能性、について取り上げる。本シンポジウムはJST-RISTEXの「科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム」の田中プロジェクト、中村プロジェクトの合同企画として開催するが、どちらのプロジェクトも「共進化」枠として行政との連携が求められており、議論の成果を政策に反映することを目指したい。
パネルディスカッション
パネリスト:菱山豊(徳島大学)、松澤孝明(文部科学省)、浅井文和(ジャーナリスト)
オンライン参加者数:120名
田中:ただいまよりウェビナー「研究公正の推進のために必要な取り組みとは」を開催します。よろしくお願いします。
本セッションは京都薬科大学の田中と大阪大学の中村さんとで進めます。科学技術振興機構の社会技術研究開発センター、JST-RISTEXの「科学技術イノベーション政策のための科学」という研究開発プログラムがあるのですが、昨年、私と中村さんがそれぞれ採択されまして、そのプログラムの一環として実施するというシンポジウムでございます。
本シンポジウムは、日本科学振興協会JAASのキックオフシンポジウムの一環として実施しているのですが、JAASは研究者だけではなく様々な立場の方に参加いただいて科学振興のために一緒にやりましょうという組織ですので、対話はひとつの大切な軸になっています。私は研究環境改善ワーキンググループと言うところに所属しており、もっぱら研究者を中心に議論する場におりますが、研究者は間違うことはあっても嘘はつかないということで社会から信頼を得ているので、研究者自身が襟を正すというか、きちんと真面目に研究することが一番大事です。キックオフでも一つは研究倫理のセッションをやりましょうというお話がJAASのメンバーから出まして、私が企画するということになりました。
研究者の方はよくご存じなのですけど、研究倫理のシンポジウムとかワークショップとかいろんな催しが増えて、研究倫理そのものは研究者にはかなり親しまれるようになってきました。悪い研究者がいるといった単純な理解ではなく、その背景にいろんな事情があることも理解していただけるようになってきました。
それでは、本日おいでいただきましたパネリストを紹介します。最初に、徳島大学の菱山さんよろしくお願いします。
菱山:こんにちは。菱山です。今日はよろしくお願いいたします。
田中:菱山さんはライフサイエンスの領域の方は特によくご存知で、研究振興、科学技術政策についていろいろご意見をいただけるということで、よろしくお願いします。
菱山:よろしくお願いします。ありがとうございます。
田中:それでは松澤さん、お願いします。
松澤:松澤です。今日はよろしくお願いいたします。いいセッションになることを期待しております。
田中:松澤さんは現在、文部科学省に所属されていますが、前職はAMEDの研究公正業務推進部の部長であり、この分野の方は良くご存知かと思いますが、非常にたくさんの研究公正、研究不正や国際的な枠組みについての論文を発表されています。よろしくお願いします。それでは浅井さんよろしくお願いします。
浅井:浅井でございます。皆さん、私はジャーナリストの立場から参加しております。浅井文和と申します。
田中:よろしくお願いします。浅井さんは朝日新聞社の元記者で、科学医療担当の編集委員などをお務めになりました。日本医学ジャーナリスト協会の会長を2020年からお務めということで、本日はメディアからのお話を伺うということで、よろしくお願いします。
田中:それではどうしてこうしたシンポジウムを企画して議論しないといけないのかということについて、研究不正が社会に与えるインパクトについてまずはお話いただこうと思います。浅井さんより話題提供いただきます。浅井さん、よろしくお願いします。
浅井:まず、なぜ研究公正が大事かということですが、裏返すと、今まで研究不正がいかに社会に対して悪い影響を与えたかということをお話したいと思います。
この10年間の大きな研究不正として、ディオバン事案と東大分生研事案を取材して記事を書いてきました。ディオバン事件とは、2013年に表面化したのですが、高血圧治療薬の大規模臨床研究のデータが捏造、改竄されて、間違った論文が発表され、それがガイドラインに載っていたという問題です。改ざんをした元製薬企業社員は、薬事法違反に問われて逮捕され起訴されたのですが、昨年、最高裁で無罪が確定しております。薬事法では無罪と言うことなのですが、裁判の過程でこの元社員がデータを改竄したということは認定されております。東京地検特捜部が押収したパソコンの消去されたデータを全部洗い出して、どのようにデータが変えられたかを調べ上げた結果です。そこまでやれば研究不正の調査はできると言うことです。裁判の中では元教授が寄附金集めのために臨床研究をやっていたという証言をしておりまして、利益相反管理、COIも深刻な問題でありました。
この事件を受けて、臨床研究法という臨床研究に関する法規制が始まっているわけです。研究不正事件によって政策が動くと言う事案です。
浅井:この調査を大学がやったのですが、実際、データ操作はあったが誰がデータを操作したかわからないという結果でした。調査に限界という言葉を何回聞いたでしょう?研究不正の報告書ではいつも「調査に限界」で、本当に国民はそうした研究を信用してくれるのでしょうか?という疑問を私は持っています。
浅井:もう一つは東大分生研の事案で、これは2014年に最終報告が出されています。この記事に書いてありますように、一つの研究室で多くの方が捏造、改竄にかかわっていることが認定されまして、33の論文で捏造、改竄があったと言う報告になっております。この発生要因を報告書は書いているのですが、学生等へ強圧的な指導があったと、過大な要求に対して無理をしてでも応えるしかないという意識を持つような環境があったと言うのが発生要因です。これ怖いですよね。つまりこの研究室に行ったら、もしかしたら私も捏造、改竄やっていたかもしれないという恐怖感を持ちました。最初からいい研究者と悪い研究者がいるわけではないのです。強圧的なところに入ってしまうと、巻き込まれてしまうということです。
ここで申し上げておきたいのは、研究不正に関与したということで懲戒処分を受けたある研究者の方は博士の学位も取り消しになりましたが、その後、別の研究機関で学び直しをなさいました。今はある大学の教員になっています。つまり、研究不正で懲戒処分を受けたら、その人の研究人生をおしまい、というわけで私はないと思うのですよね。学び直しのチャンスがあってもいいと思います。そういう方がここに来てくださればいいのです。シンポジウムに来て研究不正はどういう問題かをお話しいただく。あるいは倫理教育に関わっていただく、そういうことがあってもいいと私は思っています。
浅井:最後にまとめですが、医学分野での研究不正は大きな弊害を社会に及ぼします。研究者にとっては、共同研究者を巻き込む時間の損失、そして不正調査で多大な時間を要する。例えばガイドラインに不正な論文が載ってしまうと、医師にとっても患者にとっても不幸です。本来効き目が小さい薬が高く評価されることになってしまうと、医療費の負担増にもなってしまう。結局、医学の進展を阻害する大きな問題であるということで、研究公正を推進する必要があるということで、私のお話を終わります。
田中:どうもありがとうございます。不正のインパクトっていうのが、なかなか伝わらないところがあって。どうして倫理の講習とかするのですか?とか言われたりするのですが、本来大きな問題ですね。引き続きまして、中村さんの方から研究公正の現状について、お話しいただくことになっております。よろしくお願いします。
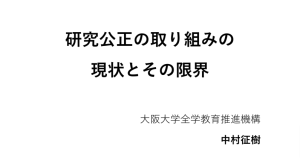 研究公正の取り組みの現状とその限界
研究公正の取り組みの現状とその限界
中村:はい、大阪大学、中村です。どうぞよろしくお願いいたします。参加者の皆さんからの質問とコメントはQ&Aの方で入れていただくという形で、是非、活発に御意見をいただければと思っております。
私の方からは、研究公正の取り組みの現状、その限界ということで話題提供させていただきます。今、浅井さんからご報告がありました東大分生研の事案ですが、2014年に最終報告がありました。丁度、STAP細胞をめぐる問題が出てきた年でもありました。私自身、その時には理研の研究不正再発防止のための改革委員会の委員等もやらせていただいて、いろいろメディアからコメントを求められることも多かったのですけれども、その中で感じていたことが、一般の方がスタッフ問題に対して非常に興味を持つのはわかるのですけれども、研究現場からするとやはり東大分生研の問題の方がより深刻ではないか、また同じような、分生研ほどではないにしても、似たような事例というのがいろんなところで起こりうる(という意味では、より深刻な問題として受け止めるべきではないか)ということです。
私自身、これまで研究不正の問題について、文科省のガイドラインづくりや、APRIN(公正研究推進協会)、学振のグリーンブック、あるいはAPRINの(作成している)e-APRINの教材、(各大学の)研究不正調査委員会の委員と、いろいろな形で研究公正にかかわらせていただいております。その中で課題と感じていることについて、いくつかお話させていただければと思います。
研究公正の取り組みの現状についてですが、文科省の委託で昨年、未来工学研究所が実施した「我が国の研究倫理教育等に関する実態調査・分析業務」の報告書というのがありまして、こちらは非常に重要な資料だと思いますので、ご覧いただけると良いかと思います。(この間、)研究倫理教育が進んできているということは、皆さん実感されているところかなと思います。(この報告書によれば、)ガイドラインができて、2015年度以降の5年間に研究倫理教育を受講した研究者は95%、学生は84%と言うことです。学生も含めて、かなり研究倫理教育が浸透してきているということかと思います。一方、その中身についてみたときに、eラーニングあるいは研究倫理教材の通読というようなことが非常に多い。(研究機関だけでなく)大学院生や研究者(個人)を対象にした調査もなされているのですが、研究者について見てみますと、具体的な事例に基づいた双方向型の研究倫理教育を受講したという人は13.6%程度で、まだ一部にとどまっています。研究倫理教育を実施することは重要だと思いますが、その内容を、より充実した、研究現場に即したもの、(研究現場で)実際に活用できるようなものにしていくことが一つの課題と考えております。
また、研究倫理教育だけではなく、例えば、研究データの管理、あるいは保存をどうするのかも重要なテーマになっていますが、研究データの保管方法を見ていくと、「それぞれの研究者が一定期間保存する」というような形がかなり多くなっている。「研究室として一定期間保存する」ということが三割、研究機関がそういう仕組みを整えているというところは15%程度ということで、(研究データの保存方法については)まだ現場の研究者に依存するというところが大きいのかなと思います。もう少し研究倫理教育だけではなく、公正性が保たれるような研究活動を推進していく仕組みをつくっていくということが非常に重要かと思っております。
全米科学アカデミーがFostering Integrity in Researchというレポートを2017年に発表しています。その中で、研究機関の責務の一つとして、研究倫理教育なども必要なのですが、それはあくまでも一部で、重要なのは研究公正をはぐくむような研究文化を創造・維持していくことだと。研究機関の責務として、不正の告発に効果的に対応できるとか、あるいはシニアの研究者が(研究公正の推進といった)ミッションを積極的にリードしたり、関与することが重要であるというようなことを指摘しております。さらに、研究倫理教育は責任ある行為を保証するための全面的な解決策とみなすことはできない、それも重要だが、包括的なアプローチの中の一構成要素と見なされるべきであると。
研究倫理教育の内容を高度化していく、実質化していくということと同時に、それ以外の取り組みも総合的に進めていくということが必要だと思います。
あと一点、研究公正、あるいは不正の問題についてどう対応していくのかということにつきまして、これも文科省の委託調査で平成31年3月に報告書がまとめられております(PwCコンサルティング合同会社「諸外国の研究公正の推進に関する調査・分析業務 成果報告書」)。こちら、文科省のウェブサイトに出ているのですが、こちらでは、我が国の研究公正や不正対応の質の向上に向けてということで、五つの論点を示しています。①研究不正への対応が、現在、研究機関によって行われているが、(その対応について)機関によって多少ばらつきがあったりする。そこを標準化して行くということが必要だ。②研究公正に係る知見やノウハウあるいは情報というものを蓄積していくということが重要になる。③国内の研究公正に携わる人材のネットワークを構築して行くことが重要である。④(研究公正に)関わる人材を育成していくことが必要。⑤「コンプライアンス戦略」としての研究公正から、「インテグリティ戦略」へと転換していく。つまり、「こういうことをやってはいけない」ということではなく、「こういう形で研究公正を推進している、公正な研究活動を、質の高い研究活動を推進していく」というような形に舵きりをして行くことが必要という論点をあげております。このあたりのことも含めて、本日議論できればと考えております。私の方からは以上です。
田中:中村さん、ありがとうございます。
まず、一つ目の話題ということで、どの辺からお話したらいいですかね?中村さん、どこからはじめましょう?
中村:まずは松澤さん、菱山さんからコメントいただいてはいかがでしょうか。
田中:では、松澤さん、お願いしていいですか?
松澤:不正の事例についても、また私のよく知らないところまで含めて、ありがとうございました。一点、先ほど中村先生からご紹介いただいた文科省の委託調査、私も当初から調査に関わっているのですが、我が国なりの研究公正システムは、2014年のガイドライン以降、非常に急速に発達してきたという印象を持っています。しかし、PwCの報告書の中にあげられていますように、我が国の場合、調査や認定の主体は大学ですし、また機関ごとの研究公正システムというのは急速に進んできているとは思うのですが、それを全体標準化して統括するような部門がまだないとかですね、海外に比べて、まだまだ新しい要素を取り入れていく部分はあるのではないかと。そういう意味では、まだ入り口に差し掛かっていて、ongoingの、途上であると言う認識が私のなかにはございます。ただ、ガイドラインみたいなものが出来ると、ガイドラインを達成していればいいのだろうという、コンプライアンス型の研究公正教育が進んで、要するに何をやればいいのかやらなければならないのかと言うところが逆に言うと一つの限界を作ってしまうような形になってしまうとすれば、むしろ絶えず研究公正を推進して行くという立場からすると、決してプラスではないのかなと。そういった意味で、絶えず研究公正を推進していくのだ、という運動をどうやって盛り上げていくかが今後の課題ではないかという印象を受けました。
田中:はい、ありがとうございます。菱山さんコメントお願いしてよろしいでしょうか?
菱山:研究公正、先ほど浅井さんが調査の限界という言葉は何度も聞いたと言う話をされていましたけれども、やはりこういうお話ってみんな実はやりたがらないですよね。嫌な話なので。実際に調査をしてくれって頼まれる先生たちというのは、こういう悪いことをやらかさない真面目に研究をやっている先生たちなのですが、調査委員会委員長やってもらったり、調査の委員になってもらったりすると、注目されてしまい、先ほど浅井さんも仰いましたが、研究時間も取られて大変エネルギーをとられます。その上に、委員長とかになると注目されて、STAP細胞のときも大変だったと思うのですけど、過去のその先生たちの論文がいろいろあら探しをされるとか、結構大変な目にあうので、調査をするとか研究公正進めましょうとか、先ほど松澤さんはそういう動きをどんどん高めましょうというふうに言っていましたが、実はそんなのみんなやりたくないんだと思うのですね。ガイドラインができる前に学術会議で科学者の行動規範を定めたのですが、浅島先生が副会長で、責任者で、それで実際に進めたのは笠木先生というもう亡くなられた東大の工学部の先生だったのですが、なかなかやっぱりどこまで誰がやるのかって。理想論はいいのだけど、全体を統合した方がいいのではないかとか、そういう話を松澤さんは指摘していたけど、いや、実はそんなみんなやりたくないですよ。関わりたくないのだと思うのですね。そういった中で、一方で、プレスの方はけしからんと言って叩いて、ともすれば研究者を追い込んで、STAP細胞のときのように笹井先生亡くなってしまいましたけど、亡くなったら亡くなったで精神的なフォローをしないのは何故だとマスコミが叩くのですが、いや、そうではなくて、あなたたちが追い込んだのでしょうということも、私は非常に強く思っているところです。叩くのは簡単で、批判することは簡単なのですが、どこまでの調査を、実際誰がやるのか、どこまで権限を持たせるのかっていうことで、お金の話は比較的単純なのですけど、研究不正の話というのは役人がいたって絶対分からないわけですね。その研究の中身が本当に不正かどうかは、特捜部の人たちがforensicでよくできたなと思うのですが、中身をみないと分からない。中身が理解できないと研究不正かどうかって普通分からないので、やはり専門家が出てこないとわからないし、一方で、その専門家ってみんなそんなことやりたくないので、その辺どうしたらいいのかというのは、確かになかなか解決方法はないなあと思うところです。
田中:はい、ありがとうございます。このセッションの前に打ち合わせした際にも、そういうお話がでて、海外と比べると、妥当かどうかわかりませんけど、研究公正に携わる人っていうのは、アメリカとかのResearch Integrity Officer (RIO)の方とかは非常に誇りを持っていて、私は立派なことをしているのだという感じでお話になるのですが、日本では建前的にもそうした声は出てこないかなと思うのですが、そのあたりの違いは何に起因するのでしょうか。
中村:その違いというわけではないのですけれども、不正調査の対応と、研究倫理教育や研究公正を推進するような仕組みをつくっていくというところは、一度切り分けて考えた方が良いのかなと思っています。私自身も研究公正に関する研究をやっているのですが、こういう分野に新しい人に入って来てもらいたいというときに研究倫理教育や、教育に限らない包括的な取り組みをどうやっていくのかっていうところだと、クリエイティブなことができるし、それが研究公正の推進につながっていくなということを非常に実感しながらやれるかなと思います。ただ、研究不正調査の対応ということになると、特にポストが安定していないと、いろんなことをやりにくいということはあります。(私自身、)大学の調査委員会の委員として参加させていただいた時に、「これは不正として判断せざるを得ない」と発言するわけですけれども、大学側としては必ずしもそう判断されることを快く思っていないということもあったりする。その中で、調査委員会の委員になるというのは、いろんなところから恨まれやすいというところがあるのかなと。そこも含めてどう対応していくのかというと、やはり一定の偉い先生方じゃないとなかなか難しいのかなと感じるところはあります。
松澤:まず、調査の話と研究公正全体をどう進めるかという話は切り分けた方がいいと思っていて、あくまで研究公正という環境をどう作っていくかということ、調査の話を進めるという話以上に、まずそういった環境作りが重要なんじゃないかということをまずはご指摘したいです。では、具体的にどういう(不正)調査をやればいいのかは、私のかつての論文にも書きましたが、国によって進め方ずいぶん違っています。アメリカのような少し強権的な研究公正、RIOみたいな方がいらっしゃる国もあれば、むしろ研究者の中の集団を中心にやっていこうというドイツみたいな国もあれば、後で話が出てくると思いますが、研究公正アドバイザー制度を設けている国と、オンブズマン制度を設けている国とでは機関との関係が随分違うのですね。研究者が専門家中心にやっているのか、もう少し機関中心にやっているのかということも、要するに(研究不正の)調べ方は色々あって、それによって出てくる結論もまちまちである。ただ、それについて一つだけ重要だと思うのは、その機関ごとによって結論がまちまちになるのではなくて、一定の社会コンセンサスの幅の中に各機関の結論が収まっていく仕組みをどうつくっていくのかというのが、昨今の各国の研究公正で、仕組みづくりとして考えられているところです。日本で議論すると、すぐ海外の研究公正としてアメリカの仕組みが出されるのですけど、アメリカの場合はアメリカの風土の中で、ああいう形しかある意味、社会的にステイブルな状況をつくることができなかったのだと思っています。そうではなくて、日本型のコンセンサスづくり、逆に言うと、機関ごとで、それぞれの結論を出していく。その機関の結論が社会的にも日本の国内でそれほどばらつきがなく、安定した形で受け止められるような仕組みをどう発展させていくのかが一つの課題であるということが、先ほどのPwCの第一番目の論点だと思っています。
田中:はい、ありがとうございます。研究機関が不正調査をするのはどこの国でも同じで日本だけではないのですが、どうしても利益相反が避けられない、不正が起こっただけで、倫理教育ができていないとか、研究者の管理が良くないとか言われるのでどうしても不正が出たとは言われたくないという力がはたらきます。いいことをやると誉めてもらえるような仕組みがあるといいのではないかと思うのですが。不正調査という側面と研究公正を分けたらいいというお話も出ていましたが、そのあたりはいかがでしょうか。浅井さんご意見ございますか。
浅井:Q&Aでジャーナリストが研究公正に貢献できることと質問が来ていますが、これにお答えした方がいいでしょうか。
田中:はい、お話に入れていただければ。
浅井:ジャーナリストから見て研究公正に貢献できるかということですが、多分、皆さんもご存知だと思いますが、アメリカでRetraction Watchというサイトがありまして、それをやっている人がIvan Oranskyさんです。画面共有しますと、この方ですよね。アメリカで研究公正に関してこのRetraction Watchは相当、大きな影響を与えたと思います。おかしな論文があるとここで指摘されると。Ivan Oranskyさんという方は、4、5年前に日本の研究公正推進連絡会議にいらっしゃって、東大の安田講堂で講演されたので、覚えていらっしゃる方も多いと思います。この方はRetraction Watchをやっているだけではなくて、アメリカのAHCJというアメリカヘルスケアジャーナリスト協会の会長をやっていた人です。つまり、研究公正の取材をやっている人がアメリカの医学ジャーナリストのトップに立っていた、それだけアメリカのジャーナリストの中では研究公正の取材をするということは重要なのだと思われているわけなのですよ。そういう意味で、研究公正に関して事実に基づいて報道していく、その場合にジャーナリストの利点というのは、横串をさせるというところですね。全国あちこちで起きている研究に関するいろんな事案を調べてデータも持っているし、裏側も結構ジャーナリストは知っていますので、一つの研究機関の中だけにいるとわからないことも、ジャーナリストであれば広く見ることができるので、そういうところから研究公正に関して、ジャーナリストが報道する、あるいは倫理教育の中にジャーナリストが参加するということができるのではないかと思っています。外からの視点を入れていくことが、今後発展していくためにも重要ではないかと思っています。
田中:はい、ありがとうございます。Iva Oranskyさんが、私は研究不正調査の方で存じあげているわけですけど、もっと大きい組織のトップであるということは、受け止めが随分違うなあと感じました。日本の研究機関が不正調査をして厳しくやったときに、それがよかったという評価になれば、一番いいのかなと思うのですけど、そのあたりは菱山さんいかがでしょうか?
菱山:誰が評価するかですよね。たぶん世の中的には、報道機関はきっと拍手をすると思うんですけど、アカデミアがそこをどう思うかですよね。厳しいのか厳しくないのかということもあるし、各機関間で差があるというのも、事案ごとに違うので、差が出るというのは比べようがないですね。厳しいか厳しくないかも一体何をもって言うのかがよくわからないのではないですかね。仕組みとしてはこういう仕組みでやりましょうという、外形的な基準は設けられると思うのです。ただ、その時に先ほどQ&Aで研究不正を防ぐ仕組みはどうなのだというコメントもありましたが、その研究不正を防ぐための管理システムを作ってしまうかどうかということもあります。厳しいかどうかも多分主観によって全然違ってくるのではないかと思うのですよね。
中村:そのちゃんとやっているかどうかは、外からは見えにくいというところがあるとは思います。外に公開されるような情報は非常に限定されているのと、あと不正と認定されなかった場合に、多くの場合、(調査結果が)公表されない。不正と認定されなかった理由は、合理性があるのかもしれないし、そうでないのかもしれない。ただ、そこのプロセスが全く外から見えないので、逆に本当にちゃんとやっているのかという懸念を産むっていうところはあるのかなと。さらに、(調査を)研究機関が実施するので、組織としての利益相反がある状況で、外から見て本当にやっているのかと受け止められてしまうところは大きいと思います。そこをもうちょっと透明性を高めていくとか、あるいは、(調査や認定にかかる)ノウハウであったり基準が明らかに共有されているのだということが見えるような仕組みが必要なのかなと考えております。
田中:例えば調査報告書は比較的アンタッチャブルな存在で、不正があった場合は、調査報告書を開示することになってはいるのですが、そういうものがこれまで蓄積されていないなと思うのですが、どこかで蓄積していくと、例えばこういうケースの場合はこれくらいが妥当、みたいな相場観が出てくるのではないかなと思っています。実際の調査委員会でも、「私、(研究不正については)全然分かりません」と仰る方に委員に入っていただくケースもあって、そういう場合、調査しながら皆さん学習して行くみたいなことに、実際にはなっています。そのあたりもう少し先回りできたら、確かに事案ごとに違うこともあるとは思いますが、もう少し均霑化できるのではないかと思います。
中村:特定不正行為等が認定された場合、その研究不正の概要とかは、2015年度以降は文科省のページに掲載されているかと思いますが、そのようなイメージですかね?
田中:同じ話になるのですが、経験を蓄積して参考にしようという方向性が弱いのかなというのは思うところで、アメリカのORIだと調査報告書は教材みたいな扱いになっていて、それを用いて研究公正について学びましょうという方向もあったと思うのです。日本の場合は教材という捉え方はないと思うのですね。
中村:やはり調査の際に知り得たことに対する秘匿義務があるので、(それを前提としたうえで、)その中で、開示されてる情報がもうちょっと増えていくことが重要なのかなと思います。(調査で知り得た事実を)勝手にほかのところで報告してしまうわけにもいかない。
田中:ORIの場合は契約するのですよね。不正が認定された研究者の人が、出していいですということサインするような形だったと思います。そうすると公開も可能ですよね。
中村:今、日本の場合ですと、文科省のウェブサイトに概要が掲載されるほかに、研究機関によってはもう少し詳細な報告書を機関のwebページで公開するところもあれば、そうでないところもあるという、その差というのが大きいのかなという。それぞれの機関が、それぞれの事案について、より具体的な報告を問題がない範囲で公開していただくことが重要と思っております。
田中:これは研究機関によりますけど、まあ後始末に報告しますみたいなものも結構ありますので、次に繋がるというか、そこから得られる教訓みたいなものがあると、いろいろな人の参考になるかなと思いました。
松澤:国にもよるのですが、研究機関ごとのいわゆる一次報告書ですよね。その一次報告書が、各機関によって分量も内容もまちまちであるというのは、どこの国でもですね、研究機関は利益相反を持っているので仕方ないだろうと、それをある程度の標準の幅の中にどう抑え込んでいくのかということが、各国いろいろ仕組みを考えているところです。最近いくつかの国で導入しているのは、まずその一次レポートを各機関に出させて、それを研究公正機関がレビューして行くと。足りないところは追加させて、足りるところについては、理由がわからないところについてちゃんと補足していくという形態が結構普及していると思うのですが、そういう意味では一次的な調査をやる機関の役割と、機関の調査が適正に行われるための監督機構、そこの役割分担については各国いろいろな仕組みを導入してきているというのが近年の傾向だと思います。我が国の状況をみますと、実際に各機関が報告についてまとめてきた後も、それぞれのファンディングエージェンシーが受理するにあたって中身を見ていますし、そういう意味では非公式の仕組みとしては、資金契約に基づいてチェックが行われているわけですけれども、各国の場合は非常に制度的にしっかりできているわけですから、データベースを作るにしても一定の標準的なデータが揃えられる形になっているという点が我が国との違いだと思います。
田中:ありがとうございます。日本の場合は、蓄積はされているが、それがシステム的ではない、あるいは管理する人が決まっているわけではないということでしょうか。
松澤:そうですね。標準化して蓄積していこうという仕組み自身がまだ成立しているわけではなくて、むしろ、各省庁や各機関、もしくは大学によっては自分で作っているところありますけど、それぞれのプレイヤーが、ボランタリーに事例を収集しているのが現状です。最近、フランスではOFISとか、台湾にも新しい機関ができましたけど、そういったところは、中央機関を作って一定の情報について蓄積しています。研究者、もしくは研究不正事案に取り掛かる調査委員会などが参考にできるような形のデータベースを作っていくという、むしろ評価機関の役割としてそういうことをやっている国も多いですね。
田中:わかりました。ありがとうございます。それでは、次のトピックに移動しましょう。もうすでに対策の方に話題が移っているような気もしますね。
中村:Q&Aの方で、分生研の報告書は教材に使えるレベルのものですというご意見がございますが、いくつかものでは報告書がすごく充実しているものもあると思います。そういうものは是非モデルケースとして、ウェブサイトに残るような形になっていく良いと思います。
田中:そうですね。良い調査報告書は、ラボの雰囲気まで伝わると言うか、研究室を運営する人にとっても非常に意味があるなという記述があるものもあって、そういうものが増えると非常に良いですよね。
菱山:分生研を含めて立派な報告書を作りましたが、やはりすごく大変だったと聞いています。多くの人はその報告書を見て、すごいねと思うと思うのですけど、そこに至るまでは先ほど申しあげたように、調査委員会の委員長とか調査員が誰かは明らかになるので、すごく攻撃されるわけですよね。せっかくみんなのために一肌も二肌も脱いで一生懸命やるのだけど、やっぱり大変だということがあったので、調査する人たちを守ってあげないといけないと思います。そうでないと今度はやり手がいなくなってしまう。
田中:先ほどちょっと中村さんからも出ていましたけど、そのあたり役割分担をやっていく必要があるのかもしれないですね。
田中:二つ目の話題に移動したいと思いますので、わたくしから話題提供致します。
現状の話、問題点とかをお話いただいているのですが、研究公正の推進をこれからどう進めるか、ものすごくたくさん論点があるので、なかなかまとめきれないと思うのですが。現在、研究倫理教育というのは、座学であったり、e-ランニングであったり、研究室の中で個別に指導者が教えているみたいなことですね。研究室の運営に問題があるということも、最近明るみ出ているところで、ハラスメントに近い問題ですとか、いわゆるシニアの研究者の(姿勢に)問題があると言う指摘もネイチャーやサイエンスの記事で出ているところです。
学会の役割というものもずっと指摘されていて、結局専門性が高い部分というのは、専門家が何がしか指針を示さないと評価できないのですが、これもあまり進んでいなくてですね、実際に学会で、例えば「うちの分野ではこのあたりは不正ですとか、そうじゃないですとか」いうことを決めているところは非常に少ないです。もう一つは、研究公正の専門家の育成と書きましたけど、これはかなり手薄というか人数が少なくて、中村さんのような見識をお持ちの専門家っていうのは、実際に日本国内で非常に少ないのが現状だと思います。
行政の方の話が二つ目の所の緑の枠のとこですが、ガイドラインの問題。2014年に研究不正をどう取り扱うかというガイドラインが出ていますが、これについても先ほど出ました利益相反の管理の問題もそうですし、各研究機関で情報の蓄積をどう生かすかとかいうのもそうなのですが、まだまだ変えられるのではないかっていう意見もございます。そして、不正調査の監視ですね。複数の研究機関を跨ぐようなケースっていうのもあるわけですけど、これもどう取り扱うかははっきり決まってないと思います。
先ほどから既に話題になっていますが、不正調査は非常に大きなリソースをかけて研究機関がやっているわけですが、それを蓄積できているのかということ、またそれが個人の努力みたいなものに頼っていると継続性がありませんので、そういう枠組みをどうして行くのか、システムとしてどうするのかっていう問題があると思います。
次にメディアなのですが、これは個人的な感想に近いものになりますが、今日、浅井さんからお話いただきました不正のインパクト、社会に与えるインパクトがまだまだ伝わっていないかなと。
スキャンダル的な捉え方で研究不正事件が消費されてしまうことが多いので、社会的に非常に問題ですよと言うことを伝えていただきたいと私は思います。
いろいろな会社で、検査の不正とか、たくさん事件が出ていますが、そういうものも高等教育において研究公正の問題が充分教育できてないということを反映しているのかなと想像しています。紙面の限界ということもあるかもしれませんが、まあ背景についても、Oranskyさんは、Retraction Watchで研究不正の背景について報道されているわけで、そういうものももっと増えてもいいのではないかと思いました。
田中:誰が研究公正を推進するのかということで、有名なのは、例えばアメリカにおける研究公正官、Research Integrity Officerですが、これは結構強面なところもありまして、法的な知識を持っている人が多いですし、不正を取り締まりおっかないイメージがあるかと思います。一方で、松澤さんからご紹介いただきました、ドイツのオンブズパーソンは、これはどちらかというとエスタブリッシュされた、尊敬される研究者がやっておられることが多くで、主に予防の方ですね、実際に事件が起こるというよりは、むしろその手前のところで助言をするというニュアンスがあるかと思います。
オーストラリアの研究公正アドバイザーは、オンブズパーソンみたいな高名な研究者というわけではないんですが、アドバイザーと言う名前の通り、助言する、サポートするという役割の色合いが強いと思います。このように、いろいろな担当官のあり方があると思うのですが、日本の研究文化みたいなものに合うような形でそうした制度がないと、うまく行かないだろうなと言うふうなことを考えているわけです。
卵が先か鶏が先かみたいな話なのですが、こうした人材、こういう業務、職務の方をどのように育てていくのかという問題は手付かずの状況です。また、欧米ではこの分野に携わっている方は尊敬されている、重要と思われているわけですが、日本の場合は必ずそうでもない。そういうところもありますので、文化的な面をどう変えていくかっていうのも大事なことと思っています。
田中:専門家の育成、ここでは研究分野をあげましたけど、実際にこういう分野の方が比較的近いわけですが、どう育成して行くかということも課題だと思います。個人的にオーストラリアの研究倫理、科学コミュニケーションの研究者とご一緒したことがあるのですが、その方は人文科学の研究者なのですが、非常に自然科学領域の研究室の主宰者に近い認識をお持ちで、驚きました。私自身は自然科学の研究者ですので、研究室の機微みたいな話はやはり実験している人でないと分からないのではないかと思っていたのですが、非常にいい感じで議論することができました。専門を極めれば、十分自然科学の研究者と同じ立場で議論ができることをよく理解しました。
既に話題に出ていますが、研究公正局的な組織をどうするのかという議論があります。いろんな事例をここに蓄積したり、あるいは啓発活動ができるといいだろうと言うことは、いろいろな方面から意見があがりますが、具体的にはどういう立て付けでやっていくかということも議論の対象になると思います。私からは以上です。
田中:研究公正の専門家の育成は、現状はどういう感じでしょうか。
中村:APRIN、研究公正推進協会の方で、研究公正に関わる人材をどういう形で認定するのかといった仕組みづくりに取り組んでいるところだと思います。研究公正には教員、研究者、あるいは事務職員といったいろいろな関わり方があると思いますが、その中で特にスペシャリストというわけではなくても、こういう問題に関わる以上は、これくらいの知識、あるいはスキルを身につけている人という形で(研究公正に関わる人材が)育っていくことが、まずは重要なのかなと思います。
松澤:今の点に関してコメントがあるのですが、研究公正の専門家という言い方をすること自身がもう既に時代遅れのような気がするのですね。各国の制度を見てみますと、研究公正にいかに多くの人を導入していくのかと、普通の研究者がいかに研究公正を身近なものに感じていくのかということが一つの政策課題になっています。先程先生の方からご紹介になったアメリカのRIO制度、ああいう制度を取っている国は非常に少なくて、政府が研究現場にまで法律で関与して行くという国はアメリカも含めて五カ国ぐらいしかないのですが、多くの先進国はむしろアドバイザー制度を採用したり、あるいはアドバイザーと違う形でオンブズマン制度を採用しています。オンブズマンとアドバイザーも随分違っていて、オンブズマンの場合は基本的に機関よりも先にオンブズマン、いわゆる研究者ありきなのですね。(オンブズマン制度が、)要するに機関の経営から独立した形で、専門家集団でその研究不正に関して評価をしていくと、機関はその評価結果に基づいて機関として講じるべき措置をやっているという形に対して、研究アドバイザー制度では、あくまで機関の一員として必要な助言を提案していくということなので、研究者の自治という形で見た場合に、オンブズマン制度とアドバイザー制度にははるかに違いがあるということは認識しておかないといけません。その三つの形態の中で、一体どの程度の距離感で、いわゆる機関や機関との関係、あるいは政府との関係というものが学会との中で構築されていくかが、各国のインテグリティシステムの違いであって、わが国の場合どの程度の距離感が良いのか、どういった制度が馴染むのかということになるのだと思います。
松澤:先ほどの専門家というと、どちらかというとオンブズマンは、高名な、非常に優秀な、研究者からも尊敬されるような研究者ということで、選ばれた人というイメージがあるのですが、むしろ研究公正アドバイザーは逆で、普通の研究者を300人400人単位で大量に育成することで、そういった文化が浸透していくことを目指す政策が、欧州諸国ではスイスとかオーストリアとかで導入されているということが現状だと思います。PIの教育問題もあると思うのですが、若手も含めて多くの方が研究公正の世界に参入できる仕組みがないと、今までの研究室の雰囲気が変わらない。多くの、ニューフェースも含めて、研究公正の問題に知識や関心を持った研究者が参画する体制をつくることによって、研究現場の雰囲気を変えていこうという一つの運動で、そういう意味で研究公正アドバイザーの役割があると思っています。研究公正の専門家という呼び方をしてしまうと、研究公正に対して特化した知識を持つ特殊な人っていうイメージがあると思うのですが、そうではなくて、多くの方が研究公正に、敷居が低い形でどんどん参入して、こうした議論を闊達に進めていけるような、そういった文化、体制づくりが一つポイントではないかなと私は思っています。
田中:補足いただきまして、どうもありがとうございます。私はまさにその研究者の中にいますけど、インセンティブがすごく弱いというのは感じるところで、そもそも研究倫理の講習会に来ないという、そういうレベルですよね。その辺りのインセンティブ、どのように研究者の方が今おっしゃったようなアドバイザーみたいな制度に乗っていけるのか、みんながということは本当にいいことだと思うのですが、どういう風に持っていけばいいのかが悩ましいところかなと思いました。菱山さん、徳島大学の副学長ということで、大学の研究者は身近だと思うのですが、そのあたりのインセンティブを働かせることはできるでしょうか?
菱山:今聞いていて思ったのですけど、まあ他人事ですよね。誰か専門家を設けると、その人のことであって自分のことではないとなるし、だけどそうではない。先ほど、浅井さんのプレゼンで自分もその立場になってみたらという話がありましたけど、自分のことにならないといけないのが一つだと思うのですね。もうひとつは、アカデミアの中の決まりごとみたいなものなので、そのコミュニティの中での決まりごとを守らなかったらだめだよねという、単純に言えばそういうことなので、自分たちの決まり事だということを上手く共有することが大事で、しかもそれはすぐそこにあることなのだという感覚を共有できることが大事なのかなと思うのですよね。
田中さんのスライドにありましたけど、行政のレベルでやれることは多分限られているので、ルール作るとか、まあルールだと本当は行政が作っていいのかっていう問題はありますが、予算措置をするとかですね、そういうところであって、本来は学会レベルで、あるいは大学レベルで、しっかり共有するということは多分大事なんじゃないかと思うのです。本来はいわゆる業界の中で、あの自分のこととして考えることが大事なのだと思うのですが、なかなかそうなってないっていうのが現状かなと思います。
田中:まさにその通りで、やはり質の高い研究を目指そうというのが、一番重要な、スローガンみたいなことになると思うのですが、駆け足の、sloppyなといいますけど、sloppyサイエンスみたいなものが非常に高く評価されているのが現状で、例えばネイチャー連発しましたみたいな、そういうことなのですが、それが高く評価されているので、アトラクティブなのだけどきっちり詰めができてない研究では?といった類の話は議論が盛り上がらないのが現状だと思っています。
そういうのが背景にあるかなということは、私が感じるところです。
菱山:報告書には一応背景とか出てきますが、背景をどういうふうに掘り起こしているのかはすごく大事なことかなと思うのですよね。こういう背景で起こったということを共有して、これはもしかしたら自分のところでも起こるのではないかと思うようにすることが大事だと思っております。
田中:浅井さんからご覧になって、私もいろいろな科学ニュースを見ていて思うのですが、すごくアトラクティブだけどちょっと危ないかなという研究は比較的人気があります。報道される方からはどうなのでしょうか。地味な研究とか派手な研究とかあると思うのですが。
浅井:私も科学報道に携わってきましたが、日本の新聞社の寂しいところは、日本の科学技術研究が世界の中のレベルで言うと相当落ちているわけですよ。それで、アメリカやイギリスでこんな凄い研究をやっていますという記事を、私もそう言うものを書こうとしたことが何度もあるのですが、新聞社の編集長からは、どうしてアメリカの話なのだ、日本の話を書けよと言われて。そうすると、非常に申し訳ないのですけど、ややレベルの低い研究も新聞で載せざるを得ないというのが、新聞社側から見た概観ですね。サイエンス的にはちょっと弱いのだけどなあというものも新聞に記事が載ってしまうこともあるし、STAP細胞の論文に関しては最初どの新聞社も気づかなかったわけですよね、不正には。そういう意味で、新聞というのも日本の科学を報道しているときに弱い立場であるし、ましてや問題になっている研究不正に関する報道というと、日本にIvan Oranskyさんのようなジャーナリストがいるのかというと、非常に少ないわけですよ。だから、そういう意味で言うと、ジャーナリストの側ももっと研究倫理、あるいは研究公正に関して学び直しをして行かないといけないという状況にあると思います。
中村:今、研究現場では、研究公正の問題、研究倫理教育も含めて、上から降ってきたっていう感覚がそれなりに大きいのかなと思っています。文科省のガイドラインが2014年に改定されて研究倫理教育をやらなくてはいけなくなったのでやる、だったりとか、とりあえず上から降ってくるものをどう対応するか、という感覚というのはそれなりにあるかなと思っています。本当にどういうことが問題なのかを考えた時に、いわゆる特定不正行為だけが問題ではないし、あるいは二重投稿とか、不適切なオーサーシップとかということだけではない。研究成果の質、あるいは信頼性を損なうような行為は問題である。そういうことを踏まえて、上からおりてきたことに対してどう対応するかというより、ボトムアップに(研究公正に関して)どういう問題が本当に重要なのか、どういう問題に対応していくべきかについて、研究現場とか研究室レベルで議論が出来るということが重要なのかなと思います。そういう意味では、このJAASみたいな組織は、分野を超えてボトムアップにそういう議論をする際に、非常にふさわしい場なのかなと考えました。
田中:コメントをいただきました。企業の方だと思うのですが、論文を成果物と考えると、出荷時に品質保証する部門というのがありますよねと言うご意見で、私は、これはCorrecting Scienceの話がそれに該当すると思っていて、修正するということですよね。研究も間違っているところや不備とか色々あるのですが、修正することに対する評価がほとんどないという現状で、例えば今までの学説に対してそれはそうではないっていう、訂正に相当するような論文を出すとか、あるいは、不正の告発もまたCorrecting Scienceだと思うのですが、いい加減な研究だという批判をするとか、そういうのは全然評価されないような仕組みになっていて、そこも変えられるといいのかなと思います。研究評価についてさらにお話しすると、話が広がってしまいますが、重要なことだと思います。
菱山:品質管理の話で、これ実は研究不正が起きる度に民間企業の方が指摘されることです。ただ、品質管理の話と研究論文の話は全然違う話だという意見が、今度はアカデミアの方からある。品質を保つためにピアレビューがあるのだと思うのですが、そのピアレビューは性善説でやっているので、巧妙な改竄などは見つけることができないと思うのですよね。
品質管理とか品質評価という観点から見ると、ピアレビューをやめて違うレビューの方式にしますかということなのかもしれないと思いました。
菱山:それから、「上から降ってくる問題」、確かにそうなのですが、それは別に日本に限らず、ORIのあの成り立ちなんか見ても(研究不正事件で)大騒ぎになって設置されたり、あるいはその前のNational Research Act(国家研究法)なんかも、大きな問題が起きてそれに対する政策としてアメリカがやってきたので、洋の東西問わず、問題が起きると政策的に手を打っていくと言うところなのかなと思いますね。一方で、中村さんの言うようにボトムアップのところをどうしていくのかは考えなければいけないし、その品質評価のやり方は大学から出ていくところで評価するのか、あるいはジャーナルのところで評価するのかっていうところはいろいろやり方はあるのかなと思います。
中村:ORIの話で言うと、(米国でも)もちろん上から降って来たものなのですが、それに対して行政サイドがどの程度の権限をもってそうした(研究不正の)問題に関わってくるのかと言うところで、(行政とアカデミアの間で)結構な対立というか、議論がありました。その中で、ORIは当初は調査をするということを重視していたのですが、そこから教育とか、研究公正の取り組みを推進するという方向にシフトしていった。それは、(研究公正の問題は)あくまでアカデミアが(主体的に)やっていくべきものだということで、例えば、National Academyの報告書などもそうですけれど、行政の関与をある程度にとどめて、その代わり自分たちでやっていくのだと動いていったことが非常に重要なところかなと思っています。
菱山:そうですね。ORIをつくったらそれで良い、今そういう乱暴な議論をする人はいなくなっているとは思うのですけど、一昔前はORIができれば何でも解決みたいなことを言う人がいました。中村さんがおっしゃったように、ORIのいろいろなことを調べてみると、それほど強権的にやるわけではなくて、アカデミアからの話もあってもっとソフトな形になったのではないかと思うのですね。強権的にやれば不正ゼロになるのかというと、そんなことはなくて。当たり前ですよね。世の中みたらいろんな犯罪が、刑法があっても起きますし、警察に捕まると分かっていてもやる人がいっぱいいるわけですから、その中でコスト−ベネフィットの関係でどこまで対策を打っていくかというところで、特にアカデミアの側では、中村さんがおっしゃったように、National Academy of Sciencesの話が出ましたが、JAASとか学術会議とかですね、そういったところでどう進めるのかを示していかないといけないと思います。私、学術会議の事務局にいた経験上、学術会議はこういうことはしっかり自分たちで考えていく必要があると思います。
田中:はい、ありがとうございます。そうですね。JAASで研究公正では何をすれば良いのだろうという話を後でやろうかなと思っていたのですけど、今いろいろご示唆いただきました。JAASのような議論の場は多くありませんので、そういう意味では貴重な場になるかなというふうに思っています。
中村:品質管理の話なのですが、どういうタイムスパンでquality controlしていくのかという時に、ピアレビューは一つ重要な役割だと思うのですが、査読が通ってjournalに掲載されたら終わりということではない。本来、そこが出発点で、その後いろいろな研究者が時間をかけてその検証したり、あるいはそれをふまえて新たなことをやったりということで、長いタイムスパンの中で評価、あるいは淘汰されていくというものだと思うのですよね。そう考えると、今の評価、あるいは予算配分の仕組みが、かなり短期的な成果に基づいて配分がなされていくというところが非常に大きいのかなと思っています。
もう少し長いタイムスパンの中で見ていかなければいけないものが、そうでなくなってしまっているっていうところが大きいのかなと思います。
田中:はい、まさに私も同感です。今ちょうど私、自分の研究プロジェクトの中で、いろいろな研究者の方にインタビューしているのですが、今、中村さんがおっしゃったことは、いろいろな研究者が指摘していて、結局どういう研究が信頼できるかというのはすぐにはわからなくてですね、何年もその研究者の活動を見る中で、これは信頼できる研究チームだということを判断していると言うお話をうかがうことが非常に多いです。今の資金配分のタームはそれとあまりマッチしてないわけですよ。その境目をぬって、不正が起こってしまうのかなっていうことも思いました。制度設計を考えると、長い目で見るとは具体的にどうするのだっていうことは難しいところかもしれませんけど、そのあたりはどうなのでしょうか?
菱山:研究の評価の問題になると思うのですが、論文の数とか引用数とかではなくて、社会的なインパクトをどうやって測るのかとかは非常に難しいところのようで、RISTEXが、さきほど標葉さんの名前も出ていましたけど、標葉さん、あるいはほかの方たちがいろいろ調べていらっしゃいます。数値で簡単に評価できるものではないとかですね、論文一つがいろいろなことに結びつくわけではないし、どうやって評価するかは難しいと思うのですけど、そこは研究途上かなと思うのです。これは日本だけではなく、イギリスでも非常に大きな課題のようであります。税金を使っているので、どれだけいい影響、あるいは悪い影響があったかについてはしっかりやっていかなければいけないけれど、そう簡単にはできていないというところかなと思います。
浅井:今日の本題の今後どういう仕組みというところなのですが、実は私も10年ぐらい前は「日本版ORIを作れ」と言っていましたし、そういう記事を書いた覚えがあります。この10年間でだいぶ変わってきていると思います。先ほど松澤先生がおっしゃった、アドバイザー制度っていうのに親和性があるなというか、日本の場合は、若い研究者の方々が受け入れやすい制度と言う意味ではアドバイザー制度という形で多くのサポーターを作っていく。ここで、一つ心配なことは、相談窓口はどうなのかという問題ですよね。自分がなんか研究不正に巻き込まれているかもしれないという時に誰に相談するというのが非常に難しいではないですか。例えばJSTの相談窓口に行けばそれで解決というわけでもないだろうし、そういう意味で何かうまい方向というか、若手の研究者、未来のある人たちに対して優しい研究公正の仕組みが必要なのだろうなと言うところが気になっているところです。
田中:ありがとうございます。研究者的には、メンターと言って、相談できる人がいるということが良いのだっていうお話がありますが、研究公正においてもそれをどう作っていくか、どんな人が?それをやればいいのかとかいうことですが、そういうことも考えないといけないと思います。
中村:現行の文科省のガイドラインの中で、告発相談の受付窓口を設けてという形になっているのですが、告発を受け付けてその後委員会に通してというプロセスと相談ではやり方が大分違ってくるので、どう相談を受け付ける仕組みを作るのかは、すごく重要な課題だなと私も考えています。
浅井:すごく心配なのは、今までの研究不正問題の歴史でいうと、研究不正を告発した方が返り討ちに遭ってひどい目にあっているっていうことがいっぱいあるわけですよ。
だから、そういう方々を守れていないという日本の社会がありまして。だから、みんな不正に気づいてもいえないし、いうのが怖い。例えば、大学の中の理事に研究公正担当理事がいても、もしかしたらこの理事は不正やっている人と仲間かもしれないと思うと言えないじゃないですか。こうしたもやもやしたところからどうやって解決するかっていうところを考えなくちゃいけないなと思っています。
松澤:我が国はアメリカ型の仕組みをガイドラインベースに作っていることもあって、要するに告発から端を発する告発窓口の整備が進んできていると思うのですね。ところが、そこに至る前のアドバイザー制度とか、オンブズマン制度をもっている各国を見ますと、告発以上に相談なのですね。オンブズマンの場合、オンブズマン自身に守秘義務があって、相談を受けた中身についてもらさないのですね。要するに、機関として介入する前段階で解消しているということで、非常に多彩な相談にのっているわけです。アドバイザーの方はあくまで機関の中の人間ですけども、研究不正に至る以前に、必要な知識を与えるということです。少なくとも、告発の窓口と相談の窓口は有効に分離しないと、こういった問題は解決しないのではないかと。ところが、特に小さい組織は、どこも組織の余裕がないとは思うのですが、専門家が一人で告発も受け付け、また相談を受け付けるということになっています。しかし、告発を取り扱う人のところにはなかなか相談はしにくいと思うのです。そうなると、かなり問題が深刻化してからしかそういった窓口に相談に来ないという、タイムラグの問題が生じてしまいます。まず疑問に思ったときに、その疑問を素直にぶつけられるような、告発とは別の形態の受付窓口をどのように普及させるか、その環境づくりが必要なのではないかと思っています。
田中:そうですね。たくさん課題があることを改めて実感しました。不正事案に至る前の相談窓口はまさに必要な仕組みで、これに加えて研究者の一つのスキル、一つの側面として、研究公正みたいな領域の知識、あるいは経験が必要というお話だと思いました。本日、私の司会ぶりがよろしくなくて、結論はこれだ、みたいな話にはならなくて申し訳なかったのですが、非常に良いヒントをたくさんいただきました。JAASがこういう話をする上で非常に良い場であるというご指摘もいただけました。我々の中で協議して、改めてフィードバックできたらと考えております。本日はありがとうございます。
田中:JSTにおける私たちのプロジェクトの紹介を簡単にさせていただこうと思います。
中村:JSTで私どもが今取り組んでいることですが、去年の10月から3年半にかけて実施するものです。研究公正規範、具体的には二重投稿とか、不適切なオーサーシップとか、そういう問題について、本来何が許容されて、何がダメなのかっていうことが明確であること、その上で研究活動を進めていくということが重要かと思うのですが、現実には特に分野によって判断の基準が違ったりする。その中で、どのような行為は行っても大丈夫なのか、何が問題ではないのかということについての認識が、必ずしも共有されていないところがあると思います。具体的に、どういう行為が問題になるのか、どういう行為が不適切なのかということが、必ずしも明確になっていないところがある。ここを解決していく。例えば二重投稿では、何が二重投稿になるのか、何が既発表となるのかというようなことについてで、研究の進め方、研究分野の特質によるかと思うのですが、学会によって、その判断基準が必ずしも統一されていない、分野による多様性があるのかなと思います。本来であれば、学会であったりその分野で、一体どういうことが許容されるのか、どういうことが望ましいのか、どんなことがダメなのか、ということを明文化するという形が理想だと思っております。学会によっては、具体的なQ&Aであったり、指針を作成しているところもあるのですが、そうではないところもかなり多いのかなと言うところです。それぞれの分野で、どういうことが許容されるのか、どういうことがダメなのかという研究公正規範を明確にするということを今、考えております。そういう中で、国内外の関連文書を収集・分析したり、編集委員を経験された研究者を対象に調査を実施して、それぞれの分野ごとにどういうことが許容されるのか、どのようなことが問題なのかということに関する具体的な基準を明らかにしていくということを進めていきたいなと考えております。研究コミュニティの役割が非常に重要だと思うのですが、その参考になるようなものを作成できればと考えております。
田中:はい、ありがとうございます。それでは私の方も紹介させていただきます。
私の方は「ライフサイエンスにおける誠実さの概念を共有するための指針の構築」というテーマでやっております。誠実さというのは非常にあいまいな概念ですが、これをなんとか言語化したいということを考えております。例えば今日もお話ししましたが、信頼できる研究者と、一緒にやるのは危ないなと感じる研究者がいるわけです。その振り分けは、ある基準のもとに考えているわけですが、なかなか言葉にはなっていません。そこでそういうものを描きたいと言うことです。現在、私が所属している学問分野でもあるライフサイエンスの研究者の方にインタビューをしているところでございます。そのインタビューの結果に基づきまして、大規模なウェブアンケートを実施したいと考えております。こちらはいずれ研究者の方にはご案内いたしますが、ぜひご協力いただきたいと考えております。このアンケートの結果をベースに、ガイドラインを作成します。これは、例えば競争的研究費の審査ですとか、あるいは人事選考、あるいは研究室の中のセミナーとか、場に応じて相応しいものをいくつか作成する予定です。健全な研究環境をつくるために役立つようなガイドラインを作り、提言することが目標です。できあがったガイドラインについては、その普及活動を進めていきたいと考えております。
元々の発想としては、研究倫理のワークショップを実施すると、研究不正なんかする人の気持ちが全然わからんとおっしゃる先生方がいらっしゃって、それはやはりその方のモチベーション、例えば新しいことを見つけたいとか、新しい治療法を開発したいですとか、そういうモチベーションが満たされている方は、まあ不正なんかしても全部寄り道ですから、意味がないっておっしゃるのですね。ということは、不正が起こるというのは、そのモチベーションがどこかで歪んでいるということが背景にあるのではと考えました。どういうときにモチベーションが歪むのか、あるいは逆にモチベーションが活かされることがあるのかということを、研究評価とも関係があると思うのですが、明らかにしたいです。
田中:本日はパネリストの皆様、大変お忙しいところご参加いただきまして、たくさんの有益なコメントをいただきました。どうもありがとうございますで、私が欲張っていろいろな話を上げてしまいましたので、ちょっとフォーカスが甘くなってしまったかなと反省しておりますが、後日資料としてまとめてウェブとかで提供できるようにと思っていますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
本日のパネリストのみなさま、どうもありがとうございました。御礼申し上げます。一言ずつお話頂いてよろしいですかね。
菱山:今日はどうもありがとうございます。結論はなかなか出ないけれども、今まさに中村さん、田中さんからのスライドにあったような取り組みをしっかりやっていくことも一つ大事だなと思って、最後のところ聞いておりました。これからもよろしくお願いします。
松澤:今日はどうもありがとうございました。私はこういった問題は、なかなか結論は出ないのだと思うのですが、こういった議論を継続すること自身が、絶え間ない研究公正の推進ということで、非常に役に立つと思います。ぜひこういう機会を定期的に作りながら、先ほどの研究公正アドバイザーじゃないですけども、普通の人がアドバイザーになれるような環境づくりを、こういったシンポジウムを契機として広げていければと、関心を持っております。先生方の努力に感謝しまして、今日はありがとうございました。
浅井:私も10年前に比べれば、研究倫理教育も遥かに普及していますし、研究公正に関して少なくとも若い学生さんの間でも話ができる状態になってきていると思うのです。ですから、今おっしゃったように本当にこういう対話を今後ずっと続けていくことによって、日本の制度にあった研究公正推進ができればいいなと願っております。よろしくお願いします。
中村:この後の時間で、もし参加いただける方は是非ご参加いただければと思うのですが、Q&Aやチャットのご意見をすべて拾えたわけではないので、それらについても議論できればと思っております。やはりこの問題について重要なことは、現場でいろいろな立場からこの問題について意見交換していく中で、本当にベターなあり方を模索していくということが非常に重要なのかなと考えております。どうぞ今後とも引き続きよろしくお願いいたします。
田中:どうも皆様ありがとうございました。引き続き、JAASでもこうしたシンポジウムの場、意見交換の場を設けていきたいと思いますので、その折にはぜひご協力の程よろしくお願いします。どうも本日はありがとうございました。
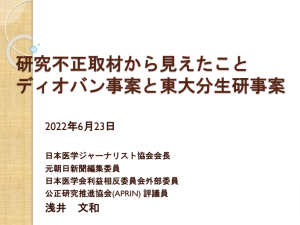 研究不正取材から見えたことディオバン事案と東大分生研事案
研究不正取材から見えたことディオバン事案と東大分生研事案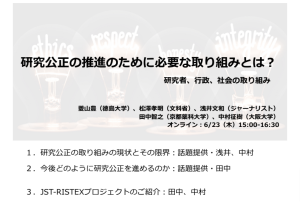 研究公正の推進のために必要な取り組みとは?
研究公正の推進のために必要な取り組みとは?